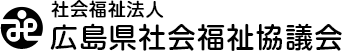「共に生きる」地域づくり 啓発パンフレット・動画
子どもから大人まで、福祉や地域づくりに関わるボランティア、専門職、NPO、企業、行政など、より多くの人が地域で“共に生きる”ことの理解を深め、共に支えあえるきっかけになるよう啓発資材(パンフレット・動画)を作成しました。
これらの啓発資材を使って、「これからの地域の理想的な姿はどんなものかな?」、「今から自分たちにできることは何だろう?」と皆さんの地域の中でアイデアを出し合ってみてください。そして、皆さんで力を合わせ、できることからアクションを起こしましょう!
啓発パンフレット 「共に生きるをかんがえる」の内容
少子高齢化が進み、ひとり世帯が増加する中で、認知症、介護、ひきこもり、子育て、しょうがい、生活困窮、病気、ケガ、自然災害などをきっかけに、人との関係をもつ機会が少なくなり、困りごとや悩みを抱え込むことで、地域の中で孤立しやすくなることが課題となっています。
そのような中で、立場や分野を越えて力を合わせ、人と人との豊かな関係性を紡ぎ直し、困りごとを抱えていても、悩みごとがあっても、どのような背景があっても、お互いに気にかけあい、受けとめあえる地域共生社会の実現に向けた取り組みの必要性が高まっています。
大切なのは「共に生きる」という考え方
広島県内の活動者や民生委員児童委員、相談支援窓口職員へのヒアリングから、孤立しやすい世帯は、次のような特徴や悩みがあることがわかりました。
- 孤立しやすい世帯の特徴
|
特徴 |
○相談できる人、頼れる人がいない ○出かける場がない ○地域とのつながりがない |
|---|---|
|
抱えている悩み |
○コミュニケーションが苦手で人との関係がうまくつくれない ○相談することが苦手で、困っていてもうまく人に説明できない ○困りごと、悩みがあってもどう対応して良いかわからない ○周囲に変に思われたくないから悩みごとを打ち明けられない |
このようなことから、相談することをためらい、人に頼ることもままならず、いつのまにか地域から孤立しやすい世帯の暮らしが見えてきました。
- 孤立しやすい世帯との関わりで大切なこと
|
○地域に生きづらさや困りごとを抱えた世帯がいることを知り、気にかける ○「こうすべきだよ」という声かけでなく、まず世帯のありのままを受けとめる ○「何かしてあげる」ではなく、相手の気持ちやこれまでの生活背景を正しく理解する ○困った時はお互いさまの気持ちで、「弱みを見せあえる関係」をつくる |
- 「共に生きる」地域に必要なこと
|
○ちょっとしたことでも相談できる、信頼できる人が身近にいること ○制度・サービスの利用で地域のつながりを切らさないこと ○自分らしくいれて「よく来たね」「いてもいいよ」と言ってもらえる居場所があること ○住民、専門職、関係者の「気になる」が自然に集まる井戸端会議のような場があること ○人とのつながりの中で、自分が誰かの役に立っていると感じられる場があること |
ひととヒトとの豊かなつながりを紡ぐ
現代社会では困りごとや悩みを抱え込みやすく、孤独・孤立を感じることは決して珍しいことではありません。だからこそ、立場や分野を越えて力を合わせ、人と人との豊かな関係性を紡ぎ直し、家族、地域、学校、会社などにおける“つながり”をより強くすることが求められています。
次の表に「共に生きる」地域づくりをすすめるポイントをまとめています。これらを参考に、困りごとを抱えていても、悩み事があっても、どのような背景があっても、お互いに気にかけあい、受けとめあえる豊かな地域づくりをめざして、共に取り組みをすすめていきましょう。
- 共に生きる地域づくりをすすめるポイント
|
信頼できる人とのつながり |
○ゆるやかにつながり気にかけてくれる人がいる ○困ったときに一緒に考えてくれる人がいる ○地域の気にかけ合いがつながり、ひろがる |
|---|---|
|
安心してつどえる居場所 |
○自分らしくいれて安心できる居場所がある ○近況を分かち合い励ましあえる居場所がある ○互いの思いや生活背景を知り認めあえる居場所がある |
|
多様な人が出会い認め合う場 |
○いろいろな立場の人が出会う場がある ○役割をもち自信や成長につながる居場所がある ○構えずに困りごとや悩みを自然と話せる居場所がある |
啓発パンフレット 「共に生きるにとりくむ」内容
共に生きる地域へのアクション「取り組み事例紹介」
各地で「共に生きる」地域をめざした取り組みがはじまっています。紹介する事例はいずれも、誰かが抱えこむのではなく地域の人とつながり、力を合わせて取り組まれているものです。「共に生きる」地域を実現するために、他地域での取り組みを知り、「これからの地域の理想的な姿はどんなものかな?」、「今から自分たちにできることは何だろう?」と皆さんの地域の中でアイデアを出し合いましょう。そして、皆さんで力を合わせ、できることからアクションを起こしてみてください!
地域の困りごとをもらさずキャッチ「身近な地域の見守り会議」(東広島市福富町)
地域の民生委員児童委員、見守りサポーター、福祉専門職などが定期的に集まり、地域の「気になる」世帯のことを話し合っています。身近に関わる地域の人と、専門的な関わりがつながり、地域とつながりを持ちにくい、声を出しにくい世帯も含めて、気にかけあい、支えあえる地域づくりに取り組んでいます。
- 概要
|
エリア |
民生委員の担当地区(福富町内10地区) |
|---|---|
|
メンバー |
民生委員児童委員、見守りサポーター、サロン世話人、福祉事業所、地域包括支援センター、生活困窮相談窓口、保健師、社協 等 |
|
内容 |
地域の「気になる」世帯のこと、見守りのすすめかた 等 |
- 「共に生きる」アクションポイント
|
○地域住民から、暮らしの中での気づきがたくさん集まる! ○専門職や行政も一緒に参加し、見過ごされがちな課題にも早期に対応できる! ○話し合いを通じて、世帯の困りごとや悩みに寄り添う協力者が増える! |

写真:地域の気になることを話合う見守り会議の様子
- 実践者の声 東広島市福富地区民生委員児童委員 門井 孝司(かどい たかし)さん
見守り会議で話し合い、「気になる」世帯に寄り添う意識が高まっています。支え合いの輪が地域全体に広がることを期待しています!
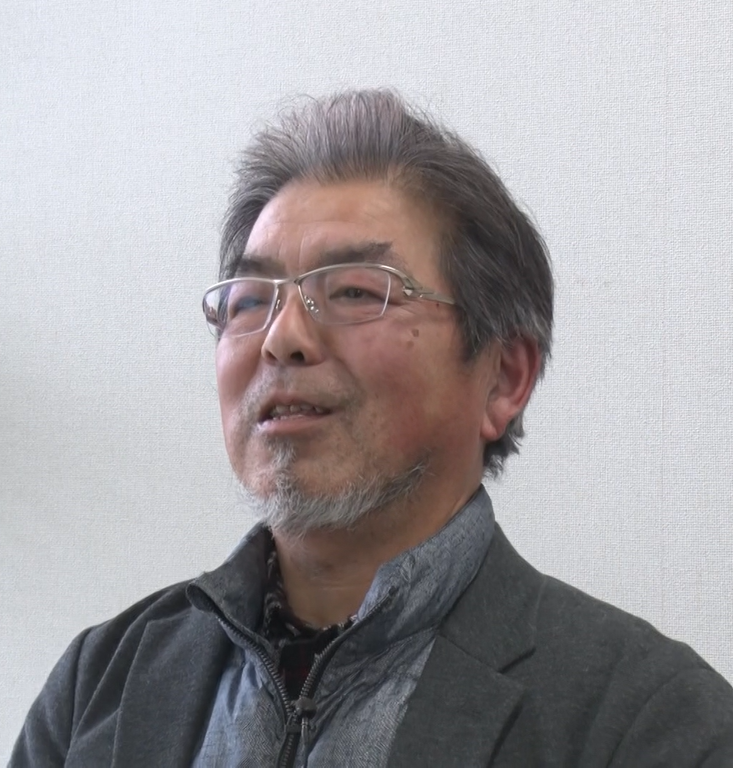
写真:東広島市福富地区民生委員児童委員 門井 孝司さん
自分らしく安心して過ごせる居場所「もうもうカフェ」(三原市久井町江木)
「歩いて行ける気軽につどえる場がほしい」「生きがいややりがいをもてる場が必要」という地域の声をもとに、2022年4月から誰もが立ち寄れるカフェを開いています。商店街の空き家を活用し、新たに地域に移ってきた世帯、生活に不安がある世帯も含め、誰もが安心して過ごせる居場所になっています。
- 概要
|
エリア |
三原市久井町江木(みはらしくいちょうえぎ)※自治区 |
|---|---|
|
メンバー |
江木自治区「もうもうカフェ運営部会」で運営(地域のボランティア) |
|
内容 |
・ゆっくりと過ごせるカフェ(毎週土曜日にランチ提供) ・住民が利用できる貸館 ・育てた野菜や手作り作品等の販売など |
- 「共に生きる」アクションポイント
|
○地域で生活に不安を抱える気がかりな世帯に声をかけ、安心してつどえる居場所に! ○カフェに訪れる人と近況を分かちあい、ちょっとした変化にも気づく機会に! ○見守りや子ども支援の経験をもつスタッフがアイデアを出し合い、やりがいある活動に! |

写真:毎週にぎわいを見せるもうもうカフェ
- 実践者の声 もうもうカフェ代表 佐倉 弘香(さくら ひろか)さん
誰も地域で孤立させないことが大切。ありのままの自分を認めあえる、ほっとする居場所づくりに取り組んでいます!

写真:もうもうカフェ代表 佐倉 弘香さん
人・物・地域がコラボする出会いの場「合同会社とこらぼ」(廿日市市津田)
「人と人がつながり、暮らしに価値を生み、元気でわくわくする地域にしたい」との思いで2021年に合同会社を設立。閉店したスーパー「ナガタストアー」の店舗を借り、「何かを始めたい」「チャレンジしたい」「交流したい」多くの世代の人が集う活動が、地域の課題解決につながっています。
- 概要
|
エリア |
廿日市市津田(はつかいちしつた)※佐伯エリア |
|---|---|
|
メンバー |
役員、アルバイト、地域のボランティア |
|
内容 |
・レンタルスペース、工房、シェアキッチンの貸し出し、小商い(こあきない)の支援 ・ハンドメイド作品、リユース商品、育てた野菜等の販売 ・イベント企画、空き家情報の紹介、健康相談など ・さとやま保健室(いきがい処方、重層的支援拠点運営、健康維持増進サポート) |
- 共に生きるアクションポイント
|
○ものづくりや地域食堂など「やってみたい」「これが好き」がつながり、多世代が集う場に! ○誰もが得意技を活かして“先生”になり、「あなたがいて助かった!」と認めあえる場に! ○公的窓口への相談をためらう人も、構えずに困りごとや悩みを自然と話せる居場所に! |
-1024x684.jpg)
写真:様々な人が集い出会いが生まれる「ナガタストアー」
- 実践者の声 合同会社とこらぼ業務執行社員 黒木 真由(くろき まゆ) さん
関わる人と生きがいを一緒に探し、大人も子どももみんなワクワクできる、帰ってきたい場から地域づくりに取り組んでいます!

写真:合同会社とこらぼ業務執行社員黒木真由さん
参考
パンフレット「共に生きるをかんがえる」 (別タブで開きます)
啓発動画「共に生きるにとりくむ」内容
お問合せ先
地域福祉課
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3414
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)