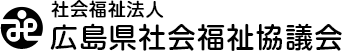福祉・介護人材のスキルアップを応援します!<社会福祉研修センターの取り組み紹介>
2025.07.10 掲載
2040年に向けて高齢者人口がピークを迎え、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える人や認知症高齢者、一人暮らし高齢者が増加することが見込まれています。超高齢・人口減少社会の進展により、生産年齢人口が激減し、あらゆる分野において労働者が不足している状況です。
また、2022年に国が実施した雇用労働調査において、初めて福祉分野で離職者が就職者を超え、2023年には全国で介護職員の人数が初めて減少に転じ、2024年の介護事業者の倒産件数は、過去最大を記録しました。
今後、福祉ニーズの高まりがますます想定される中、誰もが安心して生活できる暮らしをまもるためにも、「福祉・介護人材の確保・育成・定着」は、喫緊の重要課題といえます。
地域における福祉施設・事業所が、今後とも福祉ニーズにこたえ続けることができるように、本会の社会福祉研修センターで実施している取り組みを紹介します。
質の高い福祉サービスを提供し続けるために
これから、施設・事業所には、どのようにして新たな人材を確保するかと共に、現在従事している人材を育て、その人がやりがいと誇りをもって成長し、安心して定着できる環境整備に取り組むことが求められています。
本センターでは、福祉・介護人材の資質の向上を目的とした社会福祉従事者研修を体系的に実施し、施設・事業所に対して、職員の専門職としての段階的なスキルアップができる組織体制づくりをバックアップしています。
今回は、幅広い研修を計画的かつ体系的に実施するため、研修ニーズを分析し、1年間の研修計画を立案する役割を担う本会の社会福祉研修センター運営委員会の岡本晴美委員長(広島国際大学健康科学部教授)に、現在の施設・事業所の人材育成の課題と、社会福祉従事者の質の向上を図るための職場環境づくりについて、お話を伺いました。
インタビュー「社会福祉従事者のスキルアップの場づくりの必要性について」
広島国際大学 健康科学部 教授 岡本 晴美
1.福祉・介護現場では、人材不足が深刻化しています。これからの担い手を育てる大学側から日々感じておられることを教えてください!
高齢化による介護ニーズの増大、従事する職員の離職や高齢化など悩みの尽きない福祉・介護現場では、今もなお慢性的な人材不足の状態が続いています。当然のことながら、人材不足は高齢者の領域に限られた話ではなく、障害領域も子どもの領域も同様です。福祉・介護を志す学生の数自体が全国的に減少しているのですから、福祉現場の人材不足もさることながら、大学をはじめとする社会福祉専門職の養成校も学生募集に苦慮しています。
本学のオープンキャンパスに参加してくださった保護者様とお子様とのやりとりが記憶に残っています。お子様は「社会福祉の勉強がしたい。将来、社会福祉の現場で働きたい」一方、保護者様は「今日は、本人にあきらめてもらうために、オープンキャンパスに参加しました」と言われ、お子様の希望と保護者様の希望が真っ向から対立していました。社会福祉のお仕事は、今もなお、低賃金であるうえに身体的にも精神的にも大変というイメージがあるため、お子様に苦労をさせたくないという親心が表現されたお言葉です。保護者様が、オープンキャンパスに連れてきてくださったのは、果たして得策だったのでしょうか。私どもは、どれだけ社会福祉の仕事が魅力的かを語る言葉を持っています。そして、私どもの学生たちも。
私たちも、いつなんどき、要介護の状態になるやもしれません。そのときに、安心安全で、心地よい幸せな介護を担ってくれるのは誰でしょうか。社会福祉に興味をもち、将来の仕事にしたいと思ってくれた、このお子様のような人に担っていただきたいのではないでしょうか。自分たちの介護は、他のお子様にお任せしますか。安心して老いることができる、安心して子育てができる、安心して生活課題を抱えることができる、何かあっても大丈夫と思えるのは、サポートをしてくれる社会に信頼が置けるからこそです。現在の福祉・介護人材が不足する社会では、おいそれと病気になることも、子育てをすることも、障害や生活課題を抱えることも、老いていくことも、不安ではありませんか。
ウェルビーイング(wellーbeing)・幸福学の最高権威である慶應義塾大学大学院の前野隆司教授は、さまざまな研究にもとづき「利他的な人は幸福度が高い」と報告されています。社会福祉の仕事は、他者の幸せに関与しながら、自分も幸せになれる、とても素敵なお仕事です。そして、そんな人たちがつくる社会は、きっと将来に希望がもてる幸せな社会です。
2.人材の確保・育成・定着に向けて、施設・事業所はどのような観点で職場づくりをすすめていけばよいのでしょうか?
人材確保の問題と人材育成・定着の問題は、「鶏が先か、卵が先か論争」のようになってしまいそうですが、個人的には、育成・定着の取り組みは先決事項だと考えています。福祉の現場は、利用する人々が大切にされる場です。当然のことながら、働く人も大切にされる場であることが前提として必要です。精神論と思われるかもしれませんが、自分に余裕がないとき、人は時に意地悪になったりします。自分を大切にできる人、誰かに大切にされていると実感できる人は、他者にも優しく、大切にすることができます。福祉の現場では、このような人権感覚はとても重要です。それは、関係形成、ケアの質の向上、チームワーク、ヒヤリハットの防止などを底支えしてくれます。
このような人権感覚にもとづく価値の共有・実現が、現場で意味を持つことを実感できるような取り組みが必要なのではないかと思います。離職や転職を考える人々のお話を聞いていると、「自分が思うケアが実現できない」「周りの職員は、利用者を大切にしていない」「そのことを訴えても、理想論だと言われる」など、自分が行なっているケアに意味があるのだろうかと思い始め、悩みを深くするようです。 「意味がない」と思ってしまえば、「意味のある人生」を選択したいと思いますので、離職や転職という形で表明することも少なくありません。価値の共有・実現を実感できれば、現場は忙しくても、意味で満たされ、ふんばれたり、新たなチャレンジを生み出す宝庫となることが期待できます。
また、一緒に働くチームメンバーが志を同じくしていれば、コミュニケーションもスムーズですし、みんなと一緒に頑張っているという一体感も生まれます。「どうして私だけ大変?」といった思いが募ると負担感や不平不満が生じます。価値の共有・実現は、7割は難しいにしても、8割から9割くらいの力で働くことを可能にするかもしれません。残りの2割から1割を余力としてのこせれば、急な職員の病欠や突発的な事態が生じても、余力で対応できますので、現場に余裕が生まれます。その余裕は、誰かを思いやり、配慮することや必要な際には建設的な指摘や助言をすること、それを受け入れることを可能にするでしょう。このような職場は、突発的な事態に遭遇した際に回復する力や、問題等が発生した場合に自らの力で解決できる機能を持ち合わせ、職場が安全で健全な状態を維持できると思われます。
自分たちの親、きょうだい、子どもや孫、友人や親族にオススメできる施設・事業所とは、どのような所でしょう?その原点に立ち返ると見えてくるものがあるのではないかと思います。
3.県社協が実施している社会福祉従事者研修へのご意見や期待について教えてください!
県社協社会福祉研修センターでは、社会福祉従事者の多様なニーズに応えるべく基礎から応用まで、体系的に学ぶことができる研修の企画運営・提供を行なっています。さらに素晴らしいのは、専門職団体や高齢、障害、児童分野といった種別団体の人材・研修担当役員を構成員とする運営委員会を組織し、各団体等が実施する研修計画と当該センターが提供する研修とのすり合わせ・情報共有を行い、現場のニーズをふまえた効果的で効率的な人材育成をめざし、双方が提供する研修を活かすための協働が図られていることです。
多忙を極める現場、自施設・事業所での研修実施等が難しい現場、小規模であるがゆえに派遣研修に送り出すことが難しい現場、多様な現場の事情をふまえ、提供方法もオンデマンド・オンライン・対面など様々な工夫がなされています。
研修に参加することは、自施設・事業所、また自分自身を客観的に見つめ直すチャンスになります。多様な受講者との交流を通して、他施設・事業所の取り組みや工夫を学ぶとともに自施設・事業所での導入に思いを巡らせるだけではなく、自分が果たしてきた役割やケアの意味に気づくきっかけにもなります。また、リフレッシュや仲間づくりにもつながります。
本センターでは、広島県全体の施設・事業所のケアの質の向上、自施設・事業所に留まらない人々のネットワークの構築を研修という手段を通して実現しようとしています。今後も、時流を読みながら、柔軟に現場のニーズに応える豊富な研修メニューが開発されることと思います。施設・事業所のみなさま、社会福祉研修センターとともに行う人材育成に今後もご期待ください。
インタビューを終えて
社会福祉従事者が専門性を発揮して質の高い支援を行うためには、職場が安心安全な環境であることがとても大切であることが分かりました。このような職場づくりをすすめるためには、職員同士の人間関係やチームワーク、リスクへの対応などの組織的な配慮が欠かせません。つまり、人材育成の観点からは、職員の専門性の向上とともに「働きやすく、やりがいのある職場づくり」がのぞまれます。
本センターでは、「職場環境の整備」に関するテーマの研修を多く企画しています。さらに研修方法も、動画配信と集合型をミックスした研修などの工夫も取り入れながら、受講者がより学びやすい環境づくりにも取り組んでいます。
これからも社会福祉従事者研修をとおして、福祉・介護人材のスキルアップ支援を行い、施設・事業所の職場環境の整備を応援していきますので、研修への積極的な参加をお願いします。
本センターでは、職員階層ごとに職員の資質やサービスの質を支援するための体系的な研修メニューを準備し、テーマや課題に応じて研修内容を充実させています。主な研修について、紹介します。
社会福祉研修センターが実施する社会福祉従事者研修メニューの一部紹介
初任者を対象とした研修
「福祉施設・事業所新卒採用者研修」
福祉職員としての心がまえを学び、社会人としてのマナーを身につけ、信頼される組織人として必要な力の習得をめざします。
「中途採用者のための福祉の基本を学ぶ研修」
福祉サービスの特性を理解し、福祉職員としての基本姿勢や利用者支援の基礎知識や関わりかたを学び、就職後の悩みや戸惑いを解消し、今後の日常業務に活かすことをめざします。
中堅職員を対象とした研修
「福祉職のための伝えかた研修」
福祉職に求められる基本的なコミュニケーション手法を確認し、職場の後輩・同僚・上席者に正確に適切に伝えるための伝えかたや利用者・家族に納得していただくための伝えかたの習得をめざします。
「問題に向き合うための中堅職員の行動を身に着ける研修」
自ら問題解決に取り組む中堅職員の役割を理解するとともに、業務レベルの低下を招く、思考行動特性がないか、自身を振り返り、今後の日常業務に活かすことをめざします。
チームリーダーを対象とした研修
「OJT推進研修」
福祉職場の人材育成の意義、目的、重要性を理解し、OJTを実践するための心構えや留意点を学ぶとともに、OJTの具体的なすすめかたと手法の習得をめざします。
「業務改善向上研修」
福祉職場における業務改善の目的・本質・効果を理解し、仕事を整理整頓することで、問題の本質を見極め、課題解決に導くスキルを学び、改善意識を高め、職場での継続的な実践につなげることをめざします。
「スーパービジョン研修」
スーパービジョンの目的を理解し、必要性を確認するとともに、具体的な手法を学び、演習を通じて、自施設におけるスーパービジョン活用方法の習得をめざします。
管理職を対象とした研修
「新任管理職研修」
管理職の心構えや求められる役割を理解し、めざす管理職の姿を設定するとともに、チームを動かすリーダーシップ、マネジメントスキルの基礎を学び、チームの成果と成長に必要な手法を習得することをめざします。
「福祉施設・事業所におけるハラスメント対策研修」
ハラスメント対策の重要性を理解し、職員が安心して相談できる仕組みと対応方法を学び、職員が安心して働くことができる職場環境の整備をめざします。
「管理者に必要なストレスマネジメント研修」
管理者のストレスマネジメントにおける役割を理解し、職場でメンタルケアを行う意義を学ぶとともに、管理・監督者として自身のストレスコントロールの力を高め、職員の悩みの早期発見や不調がある人への適切な対応法の習得をめざします。
経営者(役員)を対象とした研修
「管理職・経営者のための苦情対応マネジメント研修」
組織としての苦情対応の考え方と手法の習得、苦情解決に関する組織対応の実務、クレームとカスタマーハラスメントの違いを理解します。
「社会福祉法人理事・評議員研修」
社会福祉法人を取り巻く動向や地域を支える存在としての役割を理解するとともに、適正な法人経営のための理事・評議員の役割と責任を理解し、社会福祉法人の生産性向上につなげることをめざします。
「社会福祉法人監事研修」
社会福祉法人を取り巻く動向や経営課題や適正な法人経営のための監事の役割と責任を理解し、適切な監事監査が行えることをめざします。
テーマ別の研修
「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(初任者・中堅職員・チームリーダー)」
自分自身の役割や職責を理解するとともに、演習を通して、個人とチーム・組織のために必要な強化点や改善点を発見し、自身のキャリアビジョン(何を・どのように・いつまでに)の可視化をめざします。
「災害発生時の模擬訓練から発見するBCPの課題研修」
福祉施設・事業所におけるBCP(事業継続計画)について理解し、災害発生時の模擬訓練により、自施設のBCPのウィークポイントを発見するとともに、実効性の高いBCPに向け、改善の取り組みにつながることをめざします。

写真:研修の様子。他の施設や事業所で働く仲間との多くの出会いも待っています。

詳細については、研修センターのホームページをご覧ください。
お問合せ先
社会福祉研修センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3460
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)