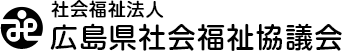障害者の生活を見守るグループホームの取り組み
2025.08.08 掲載
障害のある人たちが入居するグループホームは、地域での一人暮らしに不安のある人や、日常生活において一部介護などの支援が必要な人が、戸建て住宅やアパートで10人以下の少人数で共同生活を送る住まいです。
利用者は、「世話人」や「生活支援員」と呼ばれる職員から支援を受けながら生活しています。
広島県の発表によると、令和7年3月31日時点で、県内には606か所のグループホームが設置されています。障害のある人の増加や、誰もが安心して暮らせる地域づくりの推進により、今後ますますグループホームのニーズが高まることが予想されています。
Office M&W合同会社は、府中町内で5か所のグループホームを運営しています。
今回は、代表 渡邊美加さんと、サービス管理責任者 松本ソノさんに、運営の工夫や日々の支援で大切にしていること、そして今後の展望についてお話を伺いました。

写真:左 サービス管理責任者 松本さん、右 代表 渡邊さん お二人の間には、穏やかで温かな雰囲気が流れます
Office M&W合同会社とは
代表の渡邊美加さんは、就労支援施設や精神科病院での勤務経験を通じて、「利用者の暮らしを支える場を仕事にしたい」と考えるようになり、障害のある人が保護犬や保護猫と一緒に暮らせて、空き家も活用できるグループホーム(共同生活援助)の立ちあげを始めました。
住宅の確保に苦労するなどの課題もありましたが、2020年11月に1棟目となる Casa Activa(カサ アクティバ)を府中町内に開設しました。各棟には、保護犬や保護猫、熱帯魚がいたり、家庭菜園があったりと、個性的な特徴があります。
代表やサービス管理責任者をはじめ、スタッフ全員で、日ごろから丁寧に情報を共有し、各棟の利用者にとって心地よい居場所となるように、またスタッフにとっても働き甲斐のある職場となるように努めています。

画像:入居案内のチラシ
利用者の様子
各グループホームでは、20代から70歳近くまでの幅広い年代の人が暮らしています。ホームごとに交流の様子には違いがありますが、若い人が年上の利用者に相談したり、共に暮らしている保護犬や保護猫を囲んで会話が生まれたりと、家庭的な雰囲気が感じられます。保護犬や保護猫がいることに惹かれ、動物が好きな人が入居しています。
また、家族から自立し、離れて暮らすことで、それまでの家族との関係にも変化が生まれ、定期的に交流できるようになっている人もいます。

写真:Casa Viva(カサ ビーバ)の看板娘 ポポちゃん
利用者との関わりの中で大切にしていること
各ホームでは、月に1回、1時間程度の利用者ミーティングを開いています。 ミーティングでは、日々のできるようになったことや変化、近況、今後の楽しみ、目標など様々なことを話し合います。回を重ねるごとに、安心して自分の言葉で表現し、思いを伝えることができるようになります。話し合いを重ねていくことで、お互いの状況や人柄を理解でき、自然と協力や譲り合いの気持ちが生まれているように感じるため、丁寧に取り組むよう心がけています。
当初は前向きなことしか話せなかった利用者が、少しずつつらい気持ちや本音を語れるようになるなど、人としての成長や、ホーム全体としての成熟を感じる場面もあります。他の利用者の話を聞くことで、お互いに良い刺激を受け合っています。
また、日々の暮らしの中でも、利用者一人ひとりが自分のペースで少しずつ成長していることを感じます。 「就労に安定して通うことができるようになった」、「 明るい表情になってきた」、「一人で洗濯ができるようになってきた」などできるようになることもたくさんあります。「このホームで安心して長く生活できている」 、「入院せずに過ごせている」といった、生活を維持できていることも、かけがえのない成長の証しです。
生活の場であるからこそ、小さな変化に気づくことができ、利用者が自分らしくいられる居場所であることを大切にしています。
スタッフへの働きかけ
スタッフ同士でも、月に1回、2時間のオンラインミーティングを行い、研修や情報共有の機会を設けています。各自、自宅等から参加しており、やむを得ず欠席した場合は録画を視聴し、後日アンケートを提出する仕組みです。このアンケートからスタッフの考えていることや、工夫できる点、改善点などに気づくこともあり、全員の意見を伺える良い機会となっています。
スタッフは、一つの棟には一人の配置ですが、近い棟同士でおかずなどの調理を分担するなど協力し合いながら業務に入っています。利用者への関わりなど、支援の中で困ったことや判断に迷ったことは積極的に共有し、共通のルールを話し合って決めることで、誰もが安心して働くことができる環境づくりにつなげています。
利用者の特性によっては、対応が難しい場面もあります。そうしたときには、「できるだけ利用者さんの成長につながるよう環境を整え、温かく長い目で見守っていこう」と、スタッフ全員で心構えを共有し、常に学ぶ姿勢を心がけています。
また、主婦など福祉職未経験からスタートしているスタッフもたくさんいます。全員が病気や障害について学び、利用者へ理解を深めるようにすると同時に、仕事の中にやりがいを見出すことができるように、次のような声かけを心がけています。
「同じ地域に住むスタッフが、利用者と一緒に過ごしていること自体に意味がある。家事ひとつにしても、単なる業務ではなく、障害のある人の生活を共につくる大切な役割を担っている。ともに過ごすことで、困ったときにすぐに相談されるような信頼関係も築けていることが大事」。
このように、スタッフ一人ひとりが信頼関係の中で、日々の支援にあたっています。
利用者と地域との関わりを作るために
府中町社会福祉協議会と連携し、地域向けのボランティア講座を開催しています。令和7年度は、全5回の開催を予定しており、講座では、医師から病気や障害について、また、大学の先生から福祉制度について学ぶ機会を持っています。
そして、障害のある利用者が当事者として発表する時間を設けることにもチャレンジしています。利用者の自己表現の場を作ることで、自分の話を多くの人に聞いてもらい、質問や感想をもらえることが自信につながっています。
また、町内の障害者支援事業所の協力により、受講者が各事業所でのボランティア体験に参加できる期間も設けています。実際に利用者と一緒に過ごす体験をしてみて、一生懸命頑張って働いている姿等を初めて見て感動されたり、直接の交流を通じてお互いの理解が深まることを実感しています。ボランティア体験を通して支援の現場に触れてもらい、障害への理解を深める貴重な機会となっています。
講座終了後には、ボランティアをグループホームに招いて交流会を開くなど、地域の人々と利用者が直接つながるきっかけづくりにも取り組んでいます。
令和7年度府中町精神保健福祉ボランティア講座案内(別タブで開きます)

写真:ボランティアを招いた交流会の様子

画像:グループホームの活動を伝える「かわら版」
今後に向けての展望
今後も、地域とのつながりを深めるための行事開催に力を入れていく予定です。また、将来的に必要だと感じている取り組みが、2点あります。
一つは、65歳以上の障害のある人が、これまでの生活を無理なく継続できる場の提供です。一般的には、65歳を超えると介護保険制度の対象となり、入所施設での生活が中心となりますが、慣れ親しんだ環境から全く異なる場所に移ることは、当事者にとって大きな負担となります。現在のグループホームは、日中の外出を前提とした体制ですが、今後は介護も提供し、日中もホームで過ごせる「日中支援型グループホーム」の開設をめざしています。
もう一つは、なかなか外に出にくいなどの事情により、既存の通所サービスを利用しづらい若者にも対応できる場の提供です。具体的な内容は今後の検討課題ですが、本人のペースで安心して過ごせる居場所づくりをめざしています。
Office M&W合同会社では、障害があっても地域の中で自分らしく暮らせるよう、さまざまな工夫を重ねておられます。暮らしを共にするからこそ気づける利用者一人ひとりの変化を大切にし、利用者だけでなく、スタッフや地域の人々も安心して関われる環境づくりに取り組まれています。
こうした取り組みは、障害のある人も安心して暮らせる地域づくりの一環といえます。
広島県社会福祉協議会では、今後も支援者の皆様の実践を広く紹介し、地域福祉の推進につなげます。
お問合せ先
総務企画課
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3411
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)