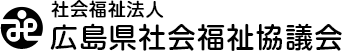専門性を活かした生活支援員の支援活動<福祉サービス利用援助事業の新たな担い手確保に向けて>
2025.11.10 掲載
福祉サービス利用援助事業「かけはし」(以下、かけはし)は、一人でものごとを決めることが不安な人に対し、契約を結ぶことにより、日々の暮らしに必要な福祉サービスの利用手続きやお金の管理のお手伝いをして、安心してくらせるよう支援する事業です。
身近な暮らしの中で困りごとに寄り添い、安心を支える「生活支援員」。近年、この役割を担う人のなかに、福祉関係者や司法などの専門資格を持つ人たちが加わっています。
世羅町社会福祉協議会(以下、世羅町社協)では、将来的に成年後見人として活躍してもらうことをめざし、社会保険労務士(以下、社労士)の資格を持つ人に「かけはし」の生活支援員として金銭管理などの支援を担ってもらう取り組みを進めています。
今回は、その新しい担い手の活動と地域に広がる期待を込めて活動の支援をしている、世羅町社協の取り組みを紹介します。
生活支援員としての活動のきっかけ
現役の社労士として働く瑞木(ずいき)さんは、「知識や経験を活かして地域に貢献したい、いつか成年後見人として地域で活動したい」という思いを抱いていました。一方で、「福祉の現場で求められる支援が自分にできるだろうか」という不安もあったといいます。
そして、地域での支援や活動について知るために、世羅町社協を訪ねました。それから数年後、世羅町社協職員のかけはし専門員(以下、専門員)から、かけはし等の権利擁護支援に関心がある人を対象とした生活支援員等の養成研修への受講を勧められ、思い切って受講することを決めました。
研修の中で実際に活動されている生活支援員の話を聞き、「自分にもできるかもしれないと思った」と瑞木さんは話ます。
この一歩が、瑞木さんにとって地域での活動を始める大きなきっかけとなりました。
社労士としての本業の傍ら、6月から生活支援員として活動し始めた瑞木さんは、月に1回、利用者に寄り添う支援をされています。
瑞木さんにインタビュー「生活支援員としての活動の実際とススメ」
活動を始めて感じていることは?
担当する2人の利用者は、性別も年齢も違います。まだ支援を始めたばかりで、1人は打ち解けてきたけど、1人は口数が少なくコミュニケーションの取りかたに悩むところもあります。こういったことも専門員に伝えながら、これから少しずつ利用者とコミュニケーションが取れるようになっていけたらいいかなと思っています。
また、支援のタイミングに合わせて専門員から年金関係の相談ができると喜んでいただけるため、社労士としての知識や経験が活かせていると感じています。
まだ活動を始めてまもないですが、専門員のサポートが手厚いため、特に負担は感じていません。これなら続けていけるかなと思っています。活動を通して、かけはしや社協の活動を知れたことも良かったです。周りも高齢化が進む中で、支援しながら知識や情報を得たり、つながりもできます。
ゆくゆくは、養成研修で学んだ、法人後見支援員にもなれたらいいなと思ったり。これから色々と勉強していきたいと思っています。
-300x200.jpg)
写真:利用者と笑顔で接する瑞木さん
活動に興味のある人・記事を見てくださった人に向けたメッセージ
活動を始めるにあたって不安もありましたが、専門員のサポートがあり安心して活動を始めることができています。
専門員は、私の事情等を考慮したうえで、支援しやすい利用者や支援する日を選定してくれます。また、担当の利用者は2人が同じデイサービスに通われているため、効率よく支援できています。
支援の流れを簡単に紹介します。まず社協へ行き、専門員から支援内容を確認した後、利用者の依頼により銀行で預貯金の払い戻しを済ませてから、2人が通うデイサービスに訪問しています。あとは1人ずつ、生活費等をお渡しして、時間が許す限り、日常会話から生活状況や困りごとなどを聴いています。それからまた社協へ戻って専門員に報告し、私自身も支援に困るようなことがあれば相談しています。
皆さんに伝えたいことは、活動に興味はあるけど私にできるかな、どうしようかなと悩まれているのであれば、まずやってみる。または、私も参加した養成研修を、まずは受講してみることをお勧めします。専門員が全面的にバックアップしてくれるので大丈夫です。安心して活動してみてください。
-300x200.jpg)
写真:利用者の依頼により郵便局で預貯金を払い戻している様子
世羅町社協の職員にインタビュー「担い手確保に向けた工夫と挑戦」
これまでも生活支援員の確保は、世羅町社協にとって大きな課題でした。
地域で支えが必要な人が増える一方で、「お願いできる人」がなかなか見つからない状況が続いていました。そんな中、社労士の資格を持つ人が生活支援員として活動してくださることになり、正直はじめは「これまでの経歴を考えると、本当にお願いして大丈夫かな」と思っていました。
でも、実際に支援が始まるとその不安はすぐに消えました。利用者の年金に関する相談にも対応できるなど、今後は、社労士ならではの専門性をいかした支援ができるのではと思うと、とても心強く感じています。
また、本業である社労士の仕事と両立しながら、無理のない形で定期的な支援を続けてくださっており、本当にありがたいです。
地域で成年後見人として活動できる人を増やしていくためには、専門性と地域性の両立が欠かせません。こうした「かけはし支援」の実践を通して、支援の経験を重ね、地域の新しい担い手が少しずつ増えていくことを期待しています。
-300x165.jpg)
写真:当時の様子を振り返る社協職員
権利擁護支援の担い手の養成と確保に向けた本会の取り組み
皆さんの地域にも「専門性や知識を活かして何かの形で地域に貢献できないか」と考えたり、定年退職後や子育てがひと段落したことで、「少しの時間なら何か社会の役に立つことができるかも」と思われる人がいるのではないでしょうか。
かけはし事業の生活支援員や、社協が担う法人後見事業の法人後見支援員は、利用者と同じ地域に暮らす住民の参加により支えられています。生活支援員等は、地域から孤立している利用者の暮らしを支えたり、地域とのつながりづくりをするうえで、とても重要で必要不可欠な存在となっています。
その反面、今後もかけはし等の利用者は増加が見込まれている中で、生活支援員等の活動自体がまだ十分に知られていない現状もあります。
本センターでは、一人ひとりが自分らしい形で地域に関わり、得意なことや経験を活かしながら支えあえるよう、地域の新たな担い手を見つけ、支援を広げていく取り組みを進めていきます。
お問合せ先
地域福祉課 あんしんサポートセンターかけはし
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-2300
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)